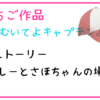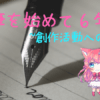【小説執筆】お仕事の実績サンプル11
 こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
管理人の春音優月(はるねゆづき)と申します。
新しく公開許可を頂いたので、ご依頼で執筆させて頂いた作品の一部をサンプル公開させて頂きたいと思います。
GLもの
※キャラクター名は、変更させて頂いております。
サンプル公開
住み慣れた都会から新幹線で地方まで乗り継ぎ、さらにローカル線で目的地へと向かい、たどり着いた駅から降りると、どこか懐かしい原風景が広がっていた。
辺り一面に田んぼがあり、遠くの方には山や森が見える。どこまで行っても緑が広がっているような風景にオリコは息をのむ。
誰もが忙しそうに早足で歩き、せかせかとした都会と違って、ここはのんびりとした時間が流れているような気がする。神様か精霊が棲んでいると言われてもおかしくないくらいに神秘的な森にも、心が揺さぶられた。
ここは、マリの祖父母の家がある場所であり、祖父母が他界した今もマリや両親が定期的に訪れている場所でもある。マリにとっては何度も訪れたところであり、よく見慣れた景色ではあるが、オリコにとっては初めて見る景色であった。
「いいところだね」
自然豊かな景色に思いがけず胸を打たれたオリコの口から、自然とそんな言葉がこぼれる。
「そうですよね! 遊ぶところもないし、本当に何もないところなんですけど、私ここが大好きなんです。先生にも喜んでもらえて良かったです」
嬉しそうな笑顔を浮かべるマリにオリコも笑みを返しつつも目的も忘れて素で感動してしまったことを反省し、どうにかいつものペースを取り戻そうとする。
「やっぱりこっちは涼しいなぁ」
立っているだけで汗が吹き出しそうになる都会のじめじめとした夏とは違い、さわやかな風が吹く田舎にマリは気持ち良さそうにしている。
「そうだね、景色も良いし、ずっとこっちにいたいくらいだね。マリちゃんと一緒に」
「先生にも気に入ってもらえたみたいで嬉しいです。仕事がなかったら、もっとゆっくりしていきたいですよね」
すかさずマリと一緒にと強調したオリコだったが、マリにはただ田舎が気に入っただけだと捉えられてしまったみたいだ。
長身かつ整ったルックスで中性的なオリコは女性にモテる女性であったが、他の女性なら秒殺のトークや意味ありげな目線をマリ相手にいくら使っても、恋愛に縁遠すぎて鈍感なマリには全く通じない。
(いつものことだけど、先が思いやられるね。
三日もあるんだ、焦る必要はないかな。
今回こそは進展させてみせるよ)
のんきに笑っているマリにオリコはめまいがしそうだったが、気を通り直して作戦を練り始める。
そもそもここに来たのは、オリコが田舎というものに来たことがないと知ったマリが、せっかくなのでお盆休みに一緒に行ってみませんか?と誘ったからだった。しかしオリコがついてきたのは田舎に興味があったからというよりも、マリを落とすチャンスだと思ったからだ。
25歳の新米獣医師マリと、27歳の科学者オリコ。
全く接点のなかった二人はオリコが街で財布を落としたことがきっかけで知り合い、友人となったが、これは最初から全てオリコの策略だった。わざと財布を落としたのも、それをきっかけにマリと親しくなろうとしたのも。
普段は優しくて愛想も良かったが、オリコには裏の顔があった。実はオリコは遠い星から調査のために地球に派遣されてきたスパイで、そのために他の女性やマリを利用してやろうとして近づいたのだ。
マリがオリコの目的に全く気がついておらず、全面的に友人として信用しきっているのはオリコにとっては好都合であったが、他の女性ならすぐにたらしこめていたのに、マリにだけはオリコも苦戦してしまっていた。
「マリちゃん、荷物少し待とうか?」
「え、あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます」
人の良さそうな笑顔で手を差し出すオリコにマリは遠慮するが、オリコがマリの肩にかけられたバッグをするりと外す。
「遠慮しないで」
強引過ぎないやり方で気を遣ってくれるオリコには、マリも照れたように笑うしかなかった。
大抵の女性なら、ここでオリコにくらっときていただろう。まあ、それも全て女性を落とすための計算なのだが……。
(どうせマリちゃんは、先生って本当にいい人ぐらいにしか思ってないんだろうけどね)
スマートで優しい女性を演じつつも、いかにしてマリを落とすかということでオリコの頭はいっぱいであった。
調査のためなのか、プライドなのか、もはや何のためなのか分からなくなっていたが、とにかくオリコにとってマリを落とさなければいけないということは、半ば使命みたいになってしまっていたのだ。
*
それから、祖父母の家に荷物を置いた二人は、まずはお墓参りをするために地元のスーパーに訪れた。
「お供物も買ったし、お花は……これでいいかな」
都会のスーパーよりもずっと品揃えが悪いスーパーで買い物するマリに付き合い、オリコも興味深そうに品物を見ていた。
オリコにとって花は女性に贈るものであって墓に供えるために購入したことはなかったし、お菓子や果物を墓前に供えるという体験も初めてであった。そもそも墓参りという文化自体がオリコの生まれた星にはないので、全てが新鮮に感じる。
お墓参りのための買い出しを終えると、そのまま歩いてお墓へと向かう。
マリは桶を取ってから一つのお墓の前まで歩いていく。簡単にお墓の回りの掃除を済ませてからお花とお供物を墓前に供え、線香に火をつけてから手を合わせる。
そんなマリを横目で見ていたオリコもなんとなく厳かな気持ちになり、マリと同じように手を合わせた。
墓の中には生身の人間は誰もいないにも関わらず、地球の人間が一生懸命お墓を綺麗にしたり、定期的に墓参りをする意味も気持ちもオリコにはよく理解出来なかったが、お墓の前に立つと、不思議と自分もそうしなければいけないような気がしたのだ。
徒歩圏内にコンビニもカラオケも駅も病院も何でも揃っている都会とは違い、ここには何もないし、別に良い景色を見ても何も得しない。
スーパーに行くだけでもだいぶ歩かなければいけないのに、ようやくあったスーパーの品揃えは悪いし、不便だし、都会に慣れたオウカからしたら得どころか損ばかりだ。でも損得勘定抜きにして、ここの景色は胸に響くものがあったのだ。
それと同じように、綺麗に掃除され、お供物が供えられたお墓が並ぶ墓前で手を合わせるマリを見て、オリコにも何か思うところがあったのかもしれない。
「おじいちゃん、おばあちゃん、今年も来たよ。お母さんもお父さんもみんな元気だから、心配しないでね。それと今年はね、友達も一緒に来てくれたの。私が友達を連れてくるなんて珍しいと思った?」
お墓に向かって話しかけているマリに、オリコが何かを言おうと口を開きかけた瞬間、二人の背後から中年女性が近づいてきた。
「あら?もしかして、マリちゃん?
そうよね。久しぶりねぇ〜」
年は、マリの母親と同じくらいだろうか。
その女性はマリを見て懐かしそうに声をかけると、マリも見覚えがあったのか笑顔になった。
「お久しぶりです」
「そちらの方は?」
「あ、先生は私の、」
友達ですと答えようとしたマリを遮るように、オリコが彼女の肩に手を回す。
「初めまして。私とマリさんはとても深い関係ですよ。また私もこちらに伺うことがあると思いますので、お見知り置きください」
笑顔のままスマートにそう答えたオリコに、中年女性もマリもその言葉の意味をすぐに理解することが出来ず、二人してキョトンとしてしまう。
オリコはあっけにとられているマリの手をごく自然にとり、それではまたと女性に挨拶をしてお墓から立ち去る。
「今日はこれからどうする?
他に行くところがあるのかな?」
「い、いえ。今日はもう特に行くところはないので、さっきのスーパーに寄って食材を買って帰ろうと思います。私の手料理でも良ければですが……」
手を繋いだまま普通に話しかけてきたオリコに、マリは戸惑いを隠すことが出来なかった。
「マリちゃんの手料理? 楽しみだな。
私も手伝うよ」
「え、あ、ありがとうございます……」
「良かったら、郷土料理教えてよ。
マリちゃんのお祖父さんやお祖母さんの話を聞きながら、二人でゆっくりしたいな。大切な人のことをもっと知りたいからね」
「あ……」
繋いだ手をぎゅっと握りしめてきたオリコに、マリは真っ赤になってうつむく。
(た、大切な人って、どういう意味なんだろう。深い意味はないのかもしれないけど、でもさっきも深い関係って……。
深い関係って、どういう意味?)
今までもオリコには何度か際どいことを言われてきたが、二人きりの時だったので友人同士の冗談、非モテの自分に気を遣ってくれてるのだとマリは思い込んでいた。
しかしマリの近所の人にまで、しかも祖父母の墓の前であんなことを言われては、さすがのマリも意識せざるを得ない。
意識しないようにしても、オリコの言った「深い関係」の意味を一度考え出したら止まらなくなり、変に意識してしまってオリコと視線を合わすことが出来なくなってしまった。
(先生の指、長くて綺麗だな……。って、同じ女性なのに、何を考えてるんだろう。でも、ドキドキしちゃう)
オリコの顔を見ることが出来なくなったマリの全神経は繋いだ手に集まり、普段はじっくりと見たことがなかったオリコの手をじっと見てしまう。今まではカッコよくて憧れの女性であり、友人だと思っていたが、もしかしたらオリコは自分のことを意識しているのかもしれない。
(こんなに素敵な人が私のことを……?
まさかね、そんなことないよね。先生ならもっと綺麗な女性でも、かっこいい男性でもいくらでも相手はいるだろうし、わざわざ私みたいな地味な女を好きにならないよね。でも……)
思わせぶりなオリコの言動、それから、繋いだ手から伝わるオリコの熱。
圧倒的に恋愛経験値が足りないマリには今の状況をどう対処したらいいのか分からず、どんどん顔が赤くなっていくばかりだった。
・
・
・
あとがき
以前ご依頼頂いた作品の続編をリクエスト頂き、執筆させて頂きました。だんだんと変化していく二人の関係がワクワクしますね。私も最終的に二人がどうなるのか楽しみにさせて頂いております。
異世界ラブ
※キャラクター名は変更させて頂いております。
サンプル公開
「ロイドくん、もしかして私たち迷ってませんか?」
黒髪を後ろで縛った地味な見た目の女性、ルナは少し不安そうに同行者である青年を見つめる。
「嬢ちゃんには言いにくいけど、迷っちまったみたいだなぁ。でも大丈夫だぜ、俺がついてるから心配すんなよ。これでも俺、傭兵だぜ?」
隣町で剣を錬成してきた二人が雪山を越えている途中、とっくに日も落ちて視界が悪くなっていたところに急に吹雪いてきたせいか、いつのまにか遭難してしまっていた。
凍えそうな寒さに歯がカチカチと震えそうなくらいではあったが、ロイドと呼ばれた青年はいつものように軽い口調でルナに笑顔を見せる。こんな状況ではあったが、いつもと変わらないロイドを見て、ルナも少しだけ笑顔を取り戻したようだ。
ルナよりもやや年上に見えるロイドは、地味な彼女とは真逆で一目を引く格好をしていた。
左目には黒い眼帯をしているが、その瞳の色は青く、肩よりも少し長い焦げ茶色の髪はセンター分けにしていて、額にはハチマキのような赤いバンダナを巻き、腰には錬成してきたばかりの剣をさしている。
肌の色も褐色がかったロイドはどこかアラブを連想させるような外見だったが、普段は傭兵として働いているため、窮地には慣れていた。だが、半年前に平和な日本からこちらの世界に転移してきたばかりのルナはそうではないだろう。
ルナを心配させないため、ロイドはあえていつも通りに振る舞い、今日はもう遅いからとりあえず近くに見える山小屋で夜を越そうと提案する。
歩ける範囲内に山小屋があったのは、不幸中の幸いだった。吹雪がおさまり、夜さえ越せば、視界も明るくなるはずだ。そう考えたロイドは、ルナが雪に足をとられて転ばないようにさりげなく彼女の足元に注意を払ってやりながら、彼女と共に小さな山小屋を目指したが……。
いざ彼らが山小屋についてみると、そこは廃墟といっていいほど古びていて、床や壁から漏れる隙間風が厳しく、食料はもちろん体を温めるための道具さえもなかった。
(せめて毛布くらいあればと思ったんだけどなぁ。見当外れだったぜ)
最初から雪山で夜を越すつもりであれば、もちろんロイドもそれなりの準備はしてきたが、そのつもりはなかったため、あいにくの軽装備だ。隣町で新しい服でも買ってきていたら良かったが、今回は剣の錬成だけで何も買わなかったことをロイドは少し後悔する。
ロイドは見当が外れたことに内心ガッカリしていたが、態度には出さずに黙って上着を脱ぐと、先ほどから小刻みに震えているルナの肩にそっとそれをかけた。
「ロイドくん、ダメです。ロイドくんが寒くなっちゃいます」
それに気がついたルナは首を横に振ってロイドに上着を返そうとしたが、ロイドはやんわりとそれを止め、再び彼女の方に自身の上着をかけ直す。
「俺はいいんだよ。ほら、俺って暑がりだろ?だから、これは寒がりな嬢ちゃんが着てくれよな」
「そう、なんですか?」
「そうだぜ? 知らなかった?」
ロイドがニッと口の端をあげると、ルナもくすりと笑みをこぼした。
ロイドが暑がりだなんてルナは聞いたこともなかったが、こんな時にもいつもと変わらず冗談を言ってなごませてくれるロイドにルナはどれだけ救われたことだろう。
ロイドから上着を借りて多少温かくはなったものの、夜の雪山の寒さを初めて体験するルナにとって、何もない山小屋で過ごす時間はあまりにも辛いものだった。時間の経過と共に氷点下の空気は容赦なくルナの体温を奪い、体力さえも奪っていく。
カーテンも何もかけられていない窓から見える景色は、未だに吹雪が続いている。外にいるよりは多少マシではあるものの、所々隙間の空いた木製の山小屋の中ではあまり変わらないかもしれない。
「初めての隣町はどうだった? 俺たちの住んでる城下町とはまた違ったんじゃねぇか?」
「そうですね。城下町にもお店はたくさんありますが、隣町はなんでも……揃っていて……」
「そうだろ? もう少し気候が良くなったら、また行こうぜ。嬢ちゃんも何かと入り用だろ?」
「はい……、そう、ですね……」
「今回は嬢ちゃんも何も買わなかったみてぇだけど、今のところは特に必要なものはねぇんだろ? 何かあったら、遠慮しないで俺に言ってくれよ。一応傭兵だから、これでも稼いでいるんだぜ?」
「えっと、はい、必要なもの……」
「嬢ちゃんが住んでた日本の服とは違うかもしれねぇが、こっちの服もそんなに悪くねぇだろ?」
「服、は……」
ルナの気を紛らわせるためにロイドがたわいもないことを話しかけていたが、寒さのせいで頭が上手く働いていないルナは会話のキャッチボールさえおぼつかない。
ブルブルと震えているルナの手足は指先までかじかみ、顔色も悪く、今にも倒れそうだった。ロイドは反射的にルナの方に伸ばしかけた手を一度は引っ込めたものの、ついには口を開くことさえも辛そうにしているルナを見兼ね、背後から小さな体を抱きしめる。
「……なっ、ろ、ろ、ロイドくん!?」
長身のロイドに包まれ、小柄なルナはロイドの胸の中にすっぽりと収まってしまう。今の今まで体の芯まで凍えそうだったルナだが、ロイドの程よく筋肉がついた長い腕や温かい体温を間近に感じ、一気に体温が上がった。青白くなっていた頬に赤みがさすどころか、首や耳までも真っ赤になってしまっている。
「こうしてたら温かいだろ? 嬢ちゃん、低体温症になる一歩手前だぜ。俺とくっつくのは嫌かもしれねぇが、少しでも暖をとらねぇとな」
「い、嫌ではないですけど……、なんていうかその、ロイドくんなら私は……、でも……、これって、あの、なんか、その……」
突然抱きしめられ、現在進行形でロイドの腕の中にいるという全く予測していなかった状況にパニックになったルナは、自分で自分が何を言ってるのかも分からなかった。
ロイドとしてはシリアスな雰囲気にならないように軽く言ったつもりだったのに、真っ赤になって口ごもっているルナを見て、これまで抑えてきた気持ちが今にも溢れそうになってしまう。どうにか自分の本心を無理矢理抑え付け、ロイドはその口を開く。
「いくら俺でもこんな状況で襲ったりはしねぇから安心してくれよ。俺のことは、毛布か布団とでも思ってくれていいぜ?」
「えっ、あ、うん、そ、そうですよね。じゃ、じゃあ、ロイドくんも私のこと布団だと思ってください」
「はは、そうだな。そう思わせてもらうぜ」
口ではそんなことを言いながらも、ロイドは内心全く別のことを考えていた。
(常に戦いの中に身を置いている俺は、いつ死んでもおかしくねぇんだ。もし嬢ちゃんと今以上の関係になっちまったら、いつか嬢ちゃんを悲しませるかもしれねぇ。だから、嬢ちゃんにはこの気持ちは伝えられねぇよなぁ。嬢ちゃんだけはダメだぜ、俺。嬢ちゃんだけは、絶対に……)
長身で容姿が整っているということもあったが、口達者なわりに裏表もなく誰にでも優しくフレンドリーに接するロイドは昔から女性には不自由したことはない。ロイド自身も女好きで、たくさんの女性と関係を持ってきたが、その実本気で惚れた相手は今腕の中にいるルナが初めてだった。
半年前、突如ルナはロイドの前に現れた。聞けば、日本とかいうロイドにとっては聞いたこともない国から来たという。
にわかには信じられることではなかったが、嘘をついている様子もなかったし、何より行く宛もなく困っているルナを放ってはおけず、ロイドは自身も住んでいる傭兵の寄宿舎の部屋をルナのために新たに借りてやり、そこに住まわせてやることにしたのだ。それからも仕事の合間に何かと世話をしているうちに、いつのまにかロイドは純粋で優しいルナに惹かれていった。
しかし、二人はキスをしたり手をつなぐどころか恋人でさえない。
今までのロイドであれば、半年もあって気に入った女性に手を出さないなんてことはありえないだろう。しかし、本気で惚れたルナには指一本触れようとはしなかった。
それも全て、ロイドが傭兵という常に命の危険と隣り合わせの職についているためだ。
もしルナと恋人になって、自分に万が一のことがあればルナを悲しませてしまう。本気で惚れているからこそ、ロイドはルナを傷つけたくないという一心で、今まで自分の気持ちに蓋をしていたのだ。
だから、こうして触れ合うことは今回が初めてなのだが……。
・
・
・
あとがき
じれじれする二人でしたが、とっても可愛いお話で私も楽しく執筆させて頂きました。
まとめ
普段自分の創作小説では、異世界を舞台にしたお話はあまり書かないのですが、ご依頼ではけっこう異世界ものをリクエスト頂けることも多いです。現代ものも異世界ものもそれぞれ別の良さがあって楽しく執筆させて頂いておりますし、勉強させて頂いてます。
可愛いものと猫と創作が大好きな物書き。
執筆ジャンルは、恋愛(TL/BL/GL/TSF)、ファンタジー、青春、ヒューマンドラマ、など雑多。年下ヒーローと年下攻めを特に好みます。
簡易プロフィールとリンク集🐱
さらに詳しいプロフィールはこちらから