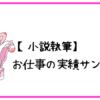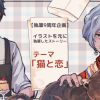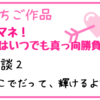【小説執筆】お仕事の実績サンプル13
 こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
管理人の春音優月(はるねゆづき)と申します。
執筆のご依頼は順調に頂いており、ありがたい限りです。
新しく公開許可を頂いたので、ご依頼で執筆させて頂いた作品をサンプル公開させて頂きたいと思います。
大学生青春もの
※キャラクター名や地名は、変更させて頂いております。
サンプル公開
「うんうん、試合前には部員全員でカツ丼を食べるんですね! 日々の練習も大事ですが、ゲン担ぎも大事ですよね」
先ほど試合を終えたばかりのテニス部部長の話を身を乗り出して聞く六反田に冷めた視線を送る。もういいだろ、と視線だけで伝えたつもりだったが、六反田には全く伝わっていないようだ。
今日は他の体育会の部活の取材も入っているというのに、試合結果には直接関係のない話までいちいち掘り下げて聞く六反田に嫌気がさす。
「本日は取材にご協力頂き、ありがとうございました。そろそろ行こう、六反田」
話が途切れたところを見計らい、半ば強引に取材を終わらせる。テニス部部長に挨拶をしてから踵を返すと、六反田が走って追いかけてきた。
「河村さん、待ってください」
俺の身長が低いこともあるが、女子の平均よりもやや高めな六反田と並ぶと、ほぼ同じ目線の高さになる。六反田の顔を見ると、明らかに不満そうな顔をしていた。
「まだ聞きたいことがたくさんあったんですよ」
「六反田、君は個人に肩入れし過ぎだよ。あれじゃ時間がいくらあっても足りない。試合に直接関係のないことまで聞く必要なんてないじゃないか」
「そんなことないです。各部の意気込みやモチベーションを保つコツを知ることでもっと応援したくなりますし、新聞を読んでくれた人ももっと大学を好きになれるはずです」
「みんなが知りたいのは試合結果だよ。余計なことを伝える必要はない」
「結果以外のことが余計なことだとは思いません。結果も大事ですが、過程も大切ですよね?」
大学内を歩きながら六反田を諭したが、何を言っても感情的に言い返され、小さくため息をつく。
俺や六反田の所属している幕張中央スポーツ編集部は、幕張中央大学体育会の機関紙であるスポーツ新聞「幕張スポーツ」を製作している。今日みたいに週末に体育会各部の試合の取材に行き、年に5回新聞を作り、学内に貼ったり学生や教職員に配っていた。
スムーズにいけばいいが、うちのミーティングでは方針を巡ってしばしば言い争いが起こる。今はミーティング中ではないが、俺の一学年下の二年生部員・六反田優樹とは考え方も性格も正反対のせいか、日頃から言い争いが絶えない。
「過程は、俺たちには関係ないことだよ。新聞なんだから、感情は出すべきじゃない」
「それは違います。私たちは幕張中央大学生として、編集部として、もっともっと体育会や大学を盛り上げるための活動や紙面構成を考えるべきですよ」
結果以外のことも大切だ、もっと体育会を応援するような活動がしたい。と繰り返し主張してくる六反田には正直うんざりしていた。
俺たちは編集部で、スポーツをする部の一員ではない。
直接試合をするわけでもない俺たちが応援したところで意味なんかないし、それが試合結果に影響を及ぼすわけでもないのに……。
*
「今度のスポーツフェスタ、俺たちも参加することにしよう」
相変わらず言い争いが絶えなかったある日。活動のために部室に集まると、四年生で編集長の西川さんが突然そんなことを言い出した。
うちの大学では毎年この時期に学内でスポーツフェスタが開かれるが、昨年も一昨年も俺たちは参加していない。
「スポーツフェスタですか?」
「うん。部員の中にはスポーツ経験が全くない人やほとんどない人もいるけど、編集部としては自分でもスポーツを経験しておいた方がいいだろ? 大丈夫、お祭りみたいなものだから、みんなで楽しもう」
なぜ突然参加しようなんて言い出したのか疑問に思って尋ねると、西川さんは温和そうな目尻をさらに下げる。
「わぁ〜! 楽しみですね! 優勝するぞ〜!!」
六反田が妙に張り切っていることが気に障ったが、西川さんの言うことなら間違いないだろう。俺もすぐに了承し、結局部員全員でスポーツフェスタに参加することになった。
*
スポーツフェスタ当日。
運動しやすい格好とシューズで体育館に集まり、自分の出番が来るのを待つ。
様々な種目がある中、俺が選んだのは卓球。
21点先取した方が勝ちのトーナメントで、出場資格は高校で部活経験がないことだ。
高校では帰宅部だったが、中学は三年間を通して卓球部だった俺にはピッタリだった。ここ数年やっていないが、これでも卓球には少し自信がある。
「Dブロック一回戦、赤い爪対ジョーカー」
アナウンスがあって立ち上がると、近くにいた嘉村さんに軽く肩を叩かれた。180cm近くある西川さんと目線を合わせようとすると、自然と俺が見上げる形となる。
「勇人の番だな。がんばれよ、赤い爪」
「はい、行ってきますね」
西川さんに返事をしてから眼鏡をかけ直し、卓球台に向かおうとしたが、俺たちの会話を聞いていたらしい六反田が目を丸くしていた。
「え、河村さんの登録名って赤い爪ですか?」
「そうだけど」
六反田の問いかけに答えると、信じられないものでも見るような目で見てくる。何がおかしいんだよ。
このスポーツフェスタでは、自分の登録名を自由に決められる。本名に近い名前で登録しても良かったが、せっかくなので全く違う名前にしようと思い、「赤い爪」にしたんだが、……。
「ちょっとダサいですよ」
「は?」
「だって、赤い爪って。どう見ても赤い爪ってタイプには見えませんし」
「だったら、君の登録名は何なんだよ。人にそこまで言うなら、よっぽどセンスの良い名前なんだろうな」
「私は、ロクタンですよ。可愛いでしょう?」
「ロクタンなて、名前をそのまま使っただけで何の捻りもない。それなら俺の方が———」
「まあまあまあ。勇人も六反田さんも落ち着いて。ほら、勇人早く行かないと。対戦相手が待ってるぞ」
険悪な雰囲気になった俺たちを見兼ねたのか、西川さんが仲裁に入る。六反田にはまだ言い足りなかったが、対戦相手をいつまでも待たせるわけにもいかない。
気分が悪いまま卓球台に向かい、ジョーカーと向かい合う。襟足まで伸びた茶髪をかき上げたジョーカーは、俺よりも身長が高く、なんとなくスポーツも出来そうな雰囲気だ。だが、卓球なら俺も負けないはず。
試合が始まると、案の定俺が優勢だった。ジョーカーは二点しか取ることが出来ないまま、結局俺の圧勝で試合が終わる。
*
「Dブロック二回戦、赤い爪対わたあめ」
体育館の隅の方で休んでいると、しばらくして二回戦のアナウンスが流れた。先程と同じ卓球台の前に行くと、そこには明るめの茶髪を上の方でおだんごにまとめた女性が立っている。
「よろしくねっ」
ニコニコしている女性———おそらくわたあめに話しかけられたが、初対面からいきなりタメ口なんて失礼じゃないか? 何年生かは知らないが、少なくとも三年生の俺よりは下に見えるし、年下でしかも初対面なら、当然敬語を使うべきだ。
少しムッとしたが、一応俺も会釈をしておく。
こう言っては悪いが、まあスポーツはあまり得意そうには見えない。今回も余裕で勝てるだろう。
「勇人がんばれよ!」
「赤い爪いけ〜!」
「わたあめ負けるな〜!」
それぞれの仲間が見守る中、試合が始まり、序盤から俺は優位に立ってリードを広げていく。今回も楽に勝てそうだな。
そんなことを思っていたのだが、……。
後半戦が始まった途端、わたあめはボールに必死に食らい付いてきた。俺がどんなに際どいところに打ち込んでもどうにかそれを拾い、ギリギリで打ち返す。チャンスボールだと思ってスマッシュを打っても、それさえも返される。
初心者じゃないのか……?
前半戦はボロボロだったのに、後半になって追い上げてきたわたあめに、正直俺も焦りが隠せない。
そんなことを繰り返しているうちに次第に点差を詰められ、ついには三点差にまで詰められてしまった。
「やったぁ! あと三点!」
「わたあめすごい! いけるよ!」
「わたあめがんばれ〜!! このまま追い越すよ!」
点を入れるたびに飛び跳ねて喜ぶわたあめや、わたあめの仲間たちの大きな声援を聞いているだけでもどんどん焦りが募ってくる。まずいな、このままじゃ……。
とにかくこれ以上点を詰められないようにしなければと、俺も必死になってボールを打ち返しす。しかし焦りばかりが募っていき、作戦も何もあったものじゃない。焦りで心臓の鼓動が異様に早くなっていく中、無我夢中でボールを打ち返したが、その際に体勢を崩し、その場に倒れてしまう。
「いっ……つ、」
「勇人!」
「河村さん、大丈夫ですか!?」
幕スポ部員たちの心配する声が聞こえたが、痛みで起き上がることが出来ない。
倒れた時に足をくじいたのかもしれないな。ズキズキと痛む右足を押さえながら、どうするべきかを考える。
棄権するか? どうせ勝っても負けてもあまり関係のないお祭りみたいなものだし、真剣勝負でもない。こんなところで意地を張って試合を続ける意味も———。
「勇人大丈夫か? あと少しで勝てるぞ!」
「河村さんがんばってください! まだ負けてませんよ!」
「最後まで諦めるな!」
「赤い爪! がんばれ〜!!」
棄権しようと口を開きかけた時、部員たちから声援が飛ぶ。
追い上げられている上に、派手に転倒までしたみっともない状態でも、まだ応援してくれるんだな。俺はもう棄権しようと思っていたのに……。
座り込んでいる俺に口々に声援を飛ばす部員の声を聞いていると、胸に温かいものが込み上げてくる。そして、不思議なことに足の痛みさえも和らいでいくような気がした。
「赤い爪さんどうしますか? 大丈夫ですか?」
「大丈夫〜?」
いつまでも座り込んでいる俺を心配した審判に声をかけられ、対戦相手のわたあめにまで心配そうな目で見られる。
俺はふっと口の端に笑みを浮かべ、痛みをこらえて立ち上がった。まだ痛むが、これくらいならどうにか続けられそうだ。
「大丈夫です。まだ出来ます」
そう答えてラケットを構えると、審判は少しためらったのち、試合開始を宣言する。
「勇人〜!!」
「河村さんいけますよ〜!」
「わたあめいけ〜!」
試合が再開してからも、相変わらず俺は中々点を決めることが出来なかったが、それでも俺を信じて応援を続けてくれる仲間たちの応援が心地良く、そして心強かった。
応援してくれるみんなのためにも負けたくない、勝ちたい。勝ちたい、勝ちたい、俺は勝ちたいんだ。
どちらも引かない接戦が続いたが、最終的には19対21という僅差で俺はわたあめに敗北した。
「きゃああああ〜!! やったあぁぁ〜」
序盤で大幅リードされていたところから大逆転勝利をしたわたあめは、Tシャツの裾からお腹が見えるほどに両手を突き上げ、大はしゃぎしている。
試合が終わってからもしばらく呆然としていたが、わたあめの喜ぶ姿を見ているうちに負けたんだという実感がジワジワとわいてきて、惨めな気持ちになった。
試合後の礼と挨拶をするためにお互いによっていくと、わたあめと視線が合う。
「ありがとうございましたっ。すっごく楽しかったよ」
キラキラした瞳で俺を見つめたわたあめは俺の手を握り、それから深々とお辞儀をした。初対面でいきなりタメ口を使ってくるような失礼な子だが、深く頭を下げるわたあめの姿を見ていたら、彼女の心からの気持ちが伝わってくる。
きっと、彼女なりに対戦相手を敬い、感謝の気持ちを示してくれたのだろう。勝っても負けても、精一杯を尽くした相手に。
「こちらこそありがとうございました。自分も楽しかったです」
わたあめにならい、俺も彼女に礼を返す。
負けたことは悔しいが、今はすごくすがすがしい気分だ。
足を引きずりながらみんなの元に戻ると、部員たちは口々に俺にねぎらいの言葉をかけてくれる。
「よくがんばったな、勇人。良い試合だったよ」
西川さんに肩を叩かれ、ありがとうございますと返すと、六反田がパタパタとこちらに駆け寄ってきた。
「すごい試合でしたね、河村さん! もう私、手に汗握っちゃいました。最後までどっちが勝つのか全然分からなくて、ハラハラっしぱなしでした。まだ心臓がドキドキしてます」
六反田は両手をグーの形にして身を乗り出し、ここがすごかっただの俺のスマッシュがどうのだのと興奮したように早口で語る。
「河村さん?」
六反田に何も言葉を返さずにいると、六反田は不思議そうに俺の顔を覗き込んできた。
「いや、みっともない姿を見せただろう? だから、てっきり君には馬鹿にされると思っていたんだ」
「そんなこと! 一生懸命がんばってた人を馬鹿にするわけありませんよ。それに、みっともなくなんてありません。最っ高にかっこよかったです!」
六反田が熱っぽくそう言うと、後ろで西川さんも大きく頷く。
「六反田さんの言う通りだ。今日の勇人はかっこよかったよ」
「六反田……。西川さん……。ありがとう、ございます……。ありがと、う……っ」
二人の言葉や俺を見守る部員たちの温かい視線に熱いものが込み上げてきて、勝手に涙が溢れる。
応援なんて意味がないと六反田の主張を切り捨て、いつもとりなしてくれている西川さんの話も話半分に聞いていたのに。こんな自分勝手な俺でも、みんなは応援して、そしてねぎらってくれるんだな。
みんなの優しさに触れ、今まで自分がどれだけ身勝手だったのかようやく分かったよ。
「六反田、今まですまなかった。応援なんて意味がないと君には言ったけど、そんなことないと今日分かったよ。君たちの応援が、すごく力になったんだ。
西川さんも、すみませんでした。人の話も聞かず、たくさんご迷惑おかけしたと思います。自分とは違う意見の部員の主張も聞くべきでした」
頭を下げて涙ながらに謝ると、誰かの手が肩に置かれる。顔をあげると、優しい目で俺を見ている西川さんと六反田と目が合う。
「やめてください、河村さん。らしくないですよ。確かに河村さんは頑固で頭が固いところがありますし、一人で突っ走っていくところがあります。でも技術は高いし正確だし、私河村さんのこと尊敬してるんですから」
「そうだよ。勇人にはこれからも期待してるからな」
「ありがとう……ございます……」
六反田は一言余計だったが、それでも二人から優しい言葉をかけられ、また俺の目から涙が溢れ出す。
「そういえば足は大丈夫だったのか? 保健室に行った方がいいんじゃないか」
しばらくそうしていたが、ひとしきり落ち着いたところを見計い、西川さんに声をかけられる。
「だいぶ痛みは引いてきましたが、念のために保健室に行ってきますね」
「ついていこうか」
「いえ、まだ他の部員の試合もあるので、応援してあげてください。自分は一人で大丈夫なので」
西川さんに挨拶をしてから、足を引きずったまま俺は一人保健室へと向かう。
*
保健室に行くと、案の定そう大した怪我ではないらしい。ほっといても直に治るということだったが、念のために手当てをしてもらう。
手当てを終えて保健室から体育館に戻ってくると、先程よりもさらに体育館が熱気と歓声に包まれていた。
何があったのか部員に聞いてみると、俺も出場していた卓球の三位決定戦が行われているらしい。
みんなの視線の先を見ると、卓球台では六反田とわたあめが激しいラリーを繰り広げていた。
「六反田、がんばれ! ロクタン!」
さっき俺がそうしてもらったように、俺は腹の底から声を出して六反田を応援する。こんなに大きな声を出したのは久しぶりだったが、自然とそうしたいと思えたんだ。
六反田に勝ってほしい、六反田を応援したい、と。
両者の仲間が声援を送る中、熱い戦いが続いたのちに六反田がかき氷を破り、六反田は見事女子最高の三位に輝いた。
「あ〜ん、もう少しだったのに〜」
「私勝ちましたか? やった! やりましたよ!」
わたあめは悔しそうにし、六反田は飛び上がって喜ぶ。しかししばらくすると、どちらも同じく晴れ晴れとした顔をして、言葉を交わしながら握手をしている。
そんなわたあめや六反田の姿を見ていると、直接戦っていない俺までもが、とてもすっきりとした気持ちになれた。
「三位おめでとう、六反田」
「ありがとうございます。本当は優勝狙ってたんですけどね。負けちゃいました」
「また次の機会に狙えばいいじゃないか。楽しかったね、今日は」
「ふふ、そうですね。すごく楽しかったです」
こちらに帰ってきた六反田に声をかけると、六反田は少し悔しそうにしながらも笑顔を見せる。
普段から対立していた六反田との距離が、なんとなく少し近づいた気がした。
他の部員も負けた悔しさやら競技の楽しさやらを口々に語り合っている。
スポーツって、こんなにも素晴らしいものだったんだな。一生懸命取り組めば、勝っても負けても清々しくてさわやかな気持ちになれる。
そして、応援してもらえれば力になるし、応援した方も選手が喜ぶ姿を見れると嬉しい気持ちになる。
今までスポーツ編集部として三年間も活動していたのに、俺はスポーツや応援の本当の素晴らしさを何も分かってなかったのかもしれない。
俺は、まだまだ未熟だ。
学ばなければいけないことがたくさんある。
未熟な俺だけど、もっとみんなにスポーツの素晴らしさを伝えたい。そして、大学や体育会をもっと好きになってほしいし、応援の大切さも伝えていきたい。
西川さんや六反田、そして他の部員から学ばせてもらい、みんなと共に成長しながら、これからもこの幕張中央スポーツ編集部でがんばっていこう。
あとがき
ご依頼者さまの設定とプロットを元に執筆させて頂きました。
こういうヒューマンドラマ系大好きなので、とても楽しく執筆させて頂くことが出来ました。
まとめ
青春ものがすごく好きで、自分でもけっこう書いてますので、青春ものをご依頼頂けるととても嬉しいですね。もちろんその他のジャンルのご依頼もすごく嬉しいです。
ご満足頂ける作品を執筆出来るようにこれからも精進していきたいと思います。
可愛いものと猫と創作が大好きな物書き。
執筆ジャンルは、恋愛(TL/BL/GL/TSF)、ファンタジー、青春、ヒューマンドラマ、など雑多。年下ヒーローと年下攻めを特に好みます。
簡易プロフィールとリンク集🐱
さらに詳しいプロフィールはこちらから