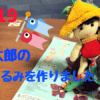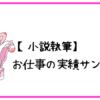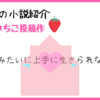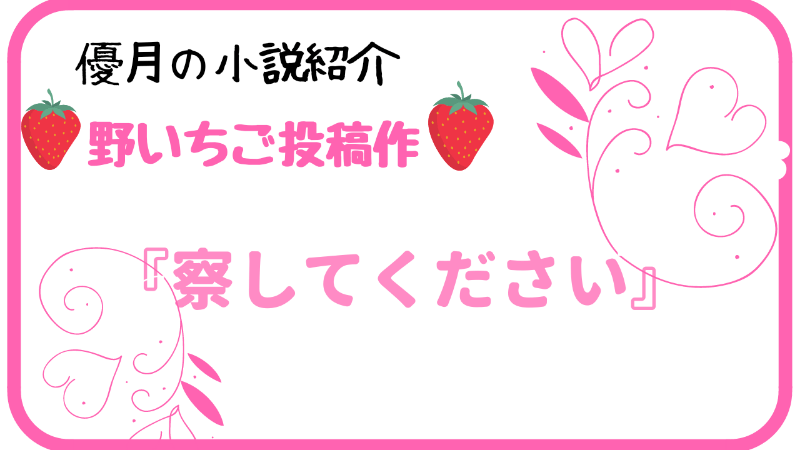【小説執筆】お仕事の実績サンプル④
 こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
こんにちは、『優月の気ままな創作活動』にお越し頂きありがとうございます。
管理人の春音優月(はるねゆづき)と申します。
自分のオリジナル小説も趣味で書いていますが、ココナラとスキマで小説執筆のご依頼もお受けしております。
非公開で書かせて頂いた小説も多いのですが、公開許可を頂いたご依頼品はいくつか当ブログでもご紹介させて頂きました。
お仕事実績①
お仕事実績②
お仕事実績③
今回の記事では、また新しく公開許可を頂いた作品を紹介させて頂きますので、ご興味のある方はよろしければご覧になっていってくださいね。
昭和風小説・姉と弟
サンプル公開
ーーー昭和××年。
中学二年生になったばかりの本間道博は、十歳年上の姉・節子の装いが最近変わってきていることが密かに気になっていた。
二人の両親は、道博が小さい頃に相次いで亡くなってしまった。頼れる人もいなかったため、まだ若かった姉が早くに就職し、貧しい家計を支えながらも道博を親の代わりに育てる以外道はなかったが、辛い環境でも節子は常に優しく、泣き言ひとつ漏らさない。
節子が就職して数年経った今も、二人は小さなアパートで一緒に暮らし、相変わらず節子はかいがいしく道博の世話をしていた。食事も作り、勉強も手伝い、中学の生活についても色々と気にかけてあげ、道重にとって節子は優しい姉であり母のような存在でもあった。
しかし、以前は地味な長いスカートをはいていた節子だったが、最近徐々にスカート丈が短くなり、とうとう太ももがあらわになるようなきわどい丈のミニスカートをはくようになったのだ。
丈は短くともデザインは品のあるものだったので、節子の清楚な印象は保たれている。しかし、そうはいっても短いものは短い。そのミニスカートをはくと節子の太ももはまる出しになってしまい、道博はいつも目のやり場に困ってしまう。
初めて見る姉の太ももは、ふっくらとしていて、見るからにすべすべしていそうでもあり、とても美しかった。もちろん今までは全く意識していなかったが、その脚のあまりの美しさに、姉も確かに女性なのだと道博は感じてしまったのだ。
両親が亡くなった頃はまだ子どもだった道博も中学生になり、異性に興味を持つような年頃になった。思春期の道博にとって、姉の生脚は目に毒だった。
十も年が離れた母親代わりの存在であり、今までは全く露出していなかった姉がいきなりミニスカートを履き始め、女を見せつけられても困ってしまう。
そんことをされたら、嫌でも異性として意識してしまう。
見てはいけないと分かっているのに、いけないことだと分かっているのに何度も見てしまう。
そのすべすべとした柔らかそうな太ももに触れたらどんな気持ちになるのだろうか、そんなことまで想像してしまうのだ。
いけないことだと思えば思うほどに姉の脚を見たい触れたいという気持ちが余計に募っていき、辛かった。
それがたまたま一日のことだったら何とかやり過ごすことができただろうが、節子はある時から毎日短いミニスカートをはくようになったのだから、道博としてはたまったものじゃない。
日に日に道博のどうしようもない思いは強くなっていき、できれば長いスカートをはいてほしいとさえ思うほどに道博は思い詰めてしまっていた。
*
ある日の夕方、畳の部屋で節子と道博はいつものように過ごしていたが、いつものミニスカートで正座をしてアイロンがけをする節子を見て、道博はひっきりなしにそわそわしていた。
「中学校はどう?
新しいお友だちはできた?お勉強はついていけてる?」
節子は丁寧にアイロンがけをしながら、何気なしに道博の学校生活について尋ねるが、正直道博はそれどころではなかった。
正座をすることによって節子のミニスカートの丈はまくれあがり、立っている時よりもさらに太もものむっちり感がくっきりと出ていてしまっている。
見ないようにはしていても、どうしても道博はそちらにばかり意識がいってしまう。机の上で宿題をやりながらも節子の脚ばかりが気になってしまい、先程から全く集中できていなかったのだ。
丈の短いスカートを履かれるとただでさえ目のやり場に困るのに、そんなスカートで正座をされると余計に困ってしまう。
どこにも逃げ場のない同じ部屋の中で、色気たっぷりの姉の脚を見せつけられたら、年頃の男子の道博としてはかなりきついものがある。
見なければ良いと言われてしまえばそれまでだが、どうすれば気にしないように平常心で過ごせるのか道博には分からなかった。
「まあ、うん、ちゃんとやってるよ。
ところで、そのスカート短すぎない?」
今まで極力気にしないように触れないように過ごしていたが、道博はもう限界だった。
限界を迎えた道博は、ついに姉のスカートについて言及してしまった。
「ああこれ?そうかしら。
気に入ったから買ったんだけど。
素敵なデザインだと思わない?」
「それはそうだけどさ……。
ストッキングは履かないの?」
「ストッキングは抵抗があるのよ。
はかない方が清楚な印象があるし、清潔感もあるでしょう?」
「そうかな。でも、何だかかえって生々しいというか……」
道博と同じ学年や一学年上の女子が思い切って脚を出していても、道博は姉の脚のような色気はきっと感じなかっただろう。
それどころか、まだ大人の色香もない少女が脚を出していても、姉の言うように清潔感があり清楚なイメージさえ抱いたかもしれない。
姉のように思い切って脚を出していても、少女らしく元気で健康的だと思ったかもしれない。
しかし、節子はもう少女と言えるような年齢ではなかった。
節子が二十歳前後の頃は、家計を支えるのに必死でミニスカートどころではなかった。
それが今になってミニスカートを履くようになったのはとある理由からなのだが、節子の年齢にふさわしいパンティストッキングを履くのはまだ抵抗があり、それならば清楚なイメージのある素脚にミニスカートというファッションにしようとなったのだ。
節子は、両親を失くしてからも泣き言ひとつ言わず、働きながら家事もして弟の面倒までみてきた。清楚でけなげとしか言いようがない人柄であり、そんな生き方をしてきた節子は、本人も清楚なことや装いを好んだ。
そういったわけで、大人の色香のありすぎるストッキングよりも清楚なイメージのある素脚を選んだのだが、節子の意識としてはそうであったとしても、客観的にみると短いスカートを素脚で履くには、節子の体はもう成熟し過ぎている。
その熟れた太ももを露出することにより、皮肉にも、ストッキングをはくよりも結果的になまめかしくなってしまっていた。
素脚のミニスカートに無理に押し込んだ大人の色香の生々しさをひしひしと感じていたわけだが、道博は上手くそれを説明することができず言い淀んでしまう。
「そう?」
道博が遠回しに節子の生脚の生々しさや色気を指摘しても、節子はあまり気にしていない様子だった。
「姉さんが脚をそんなに出してるの初めて見た気がするよ。いや、きれいだけどね」
「まあ。道博もそんなことを言うようになったのね」
道博が思い切って言ったこともやっぱり節子は大して気にもとめず、あっさりとかわしてしまう。
身近にいる姉に異性を感じてしまい、毎日その脚から溢れ出る色香を意識してしまう道博の苦しみも辛さも、節子は全く気づいていなかった。
道博も異性を意識してもおかしくない年頃であるにも関わらず、節子にとっては道博はいつまでも手のかかる可愛い弟でしかない。
小さな頃から母親代わりとして面倒を見て、一緒にお風呂にも入っていた弟に意識されているなんて、節子の方はみじんも思っていなかった。
そういった節子の無自覚が、道博を余計に苦しめていた。
*
道博が姉への行き所のない気持ちを抱えて過ごしていたある日。
街の小さなパーラーで、一組の男女が二人の今後について話し合っていた。
「節子さん、もう少し待ってもらえないだろうか。妻とのことは必ずはっきりさせるから」
もう若いとは言えないが、落ち着いた大人の魅力のある和彦は隣にいる女性に語りかける。
短いスカートからむっちりとした太ももを丸出しにしている女性は、道博の姉の節子であった。実は、節子は妻子のある和彦に恋をしていたのだ。
今までは弟を育てることに必死だった節子も、恋をして初めてミニスカートを履きたいと思うようになった。
こんなにも思い切って脚を出すのにはもちろん恥ずかしさもあったけど、少しでも女性らしくなりたい、和彦のために綺麗になりたいという思いの方が上回ったのだった。
「待ちますわ、私。あなたと一緒になれるのなら、いつまでも待ちます」
節子はハンドバッグを握りしめ、瞳をうるませながらもはっきりとそう言った。
決して泣いてすがるわけでも、別れるように強く迫るわけではなかったが、その口調からは節子の思いの強さが感じ取れる。
清楚で慎ましい性格でありながらも、やはり節子も女性であったのだ。たとえ人のものであったとしても、恋をした男性を諦めることなどできない。
「節子さん……」
節子の思いの強さを感じ取った和彦も、節子を愛おしそうに見つめる。
妻子のある和彦の言葉はどこまで本気かは分からないが、もし一時の感情であったとしても、和彦の節子に対する思いも確かに本物であった。
*
(その男は誰だよ、姉さん。
姉さんはその男が好きなの?
あんな男のために、姉さんは短いスカートを履くようになったの?)
道博は、少し離れた席で姉と見知らぬ男とのやりとりを見守っていた。学校帰りに偶然姉を見かけた道博は、なぜか胸騒ぎがして姉の後をこっそりつけてきてしまったのだ。
ミニスカートの脚にハンドバッグを乗せ、それを握り締めて男を見つめている姉。その女性は確かに道博の姉の節子であったが、まるで知らない女性のようであった。
いつもと同じミニスカートを履いていても、その艶っぽさは、家にいる時の比ではない。
好きな男の前にいる節子の太ももはピンク色の火照りを帯びて、なんとも生々しく肉感性を増していた。
和彦が去ると、道博はすぐに姉のもとへと向かい、そして、開口一番こう言った。
「姉さん、姉さんはあの男の趣味でそんなに短いスカートをはくようになったの?」
「道博……?そんな……、そういうことじゃないわ。これは……、私がはきたくなっただけよ」
いつから見られていたのだろうか。
いきなり道博が現れたことにも驚いたが、彼の言葉にさらに節子は驚いた。
妻子ある和彦との関係は、弟には絶対に知られるわけにはいかない。
どうにか節子がその場を取り繕おうとしたが、興奮状態の道博の耳にはその言葉さえも届かなかった。
母親のように慕い、尊敬している大好きな姉。
姉に対して欲望を抱くなど間違ったことだとは道博も分かってはいたが、なまめかしい色気のある美しい脚を見ると、どうしても欲を感じてしまう。
今までは限界ギリギリではあったが、なんとか欲望を抑えていた。しかし、自分の姉が見知らぬ男といるところを見てしまったことにより、道博の気持ちはついに爆発しそうになっていた。
自分が触りたくても触れない姉の脚に、あの男は自由に触れることができるのか。
節子をあの男から取り返したい。
自分だけの姉でいてほしい。
感情が爆発した道博は、とうとう姉のむき出しの太ももに手をかけた。
「や、やめなさい。こんなところで何をするの、道博」
節子が道博の手を制しても、道博はお構いなしに姉の脚に手を置き、勢いに任せてそのつややかな太ももをさすりあげる。
「姉さんの脚を見ているとたまらなくなるんだよ」
道博は熱っぽい目で姉の顔と脚を交互に見つめながら、そのハリのある柔らかな肌をさすり続ける。
白くすべすべな節子の脚は、中学二年生の男子らしい道博の筋肉質な脚とは全く違った。
ちょうどいい肉付きの太ももは想像以上に柔らかく、いつまでも触っていたいくらいに触り心地が良かった。ただ弾力があるだけではなく、女性特有のしっとりした吸いつくような柔らかさ。
一度目こそ制したものの、可愛い弟を強く拒絶することもできず、節子は股を閉じて必死に耐えているようだった。
和彦との関係を知られたかもしれない、そう思った時よりもさらに節子は動揺していたが、節子にも姉としての威厳があるのでそれを悟られるわけにもいかない。
きゅっと唇を結んで威厳を保とうとしていたが、しかし弟に脚を触られて動揺していることは完全には隠しきれず、ほんのわずかに恥じらいがにじみ出ていた。
「道博にこんなことをされるなんて思わなかった。姉さん恥ずかしいわ」
「こんなのはいてるからだよ」
道博から言われた言葉にうつむき、頬を染めて恥じらう姉の姿は新鮮だった。
姉としての威厳を保とうと冷静を装うが、異性として全く意識していなかった弟に脚を触られ恥じらう節子はとても可愛いらしく、道博の恋人か、妹のようにも思えた。
「そういえば、道博は昔からプリンが大好きだったわね。せっかくだし、食べていく?」
節子は弟からむき出しの脚をスリスリとさすられるのをただじっと耐えていたが、ある時ポツリとそんなことを言った。
血の繋がった弟に脚を触られているという奇妙な状況で、なぜいきなりそんなことを言い出したのかは節子にさえ分からない。
もちろん実の弟からの行為を受け入れることもできないが、かといって大切な可愛い弟のことを完全には拒絶できない節子には、話をそらすということしか出来なかったのかもしれない。
「……いつの話してるんだよ、姉さん。
もう子どもじゃないんだから、プリンなんて食べないよ」
両親が亡くなってからは食べていくので精一杯で、外食なんてめったに出来なかったが、プリンが大好物の道博のために節子はよく手作りしていたし、たまの贅沢で外食する時は、必ずといっていいほど道博はプリンを頼んだ。しかし道博が中学生になる頃にはプリンを頼むこともなくなったが、……。
それなのに、なぜ姉は今さらそんな思い出話をするのか。いつまで子ども扱いするのか。
それに、どうしてこんな時にそんな話をするのか……。
道博には、節子の真意が分からなかった。
「ふふ、そう?
たまにはいいじゃない。
姉さんも久しぶりにプリンが食べたいわ」
節子はそんなことを言って余裕なようにも見えたが、話をしながらも、節子の意識は常に自分の脚を触っている弟の手の感触を強く感じていた。
弟の手は、いつのまにこんなにも大きくなっていたのだろう。
小さな頃は危なっかしく、どこにいくにも手を繋いでいたが、いつからか手を繋ぐこともなくなった。
自分よりもずっと小さかった手が、いつのまにか自分の手の大きさを余裕で越し、たくましい男性の手になっていることに節子は気づかなかった。気づけなかった。
あんなに小さかった弟がいつのまにか少年から男性へと成長していたなんて……。
そんな思い出話を続ける二人は、はたから見たらごく普通の姉弟に見えただろう。しかし、誰にも見つからないようにテーブルの下で弟が姉の脚をさすっている。
非日常であり、積極的に受け入れられることはできなかったが、不思議と節子は嫌悪感を感じていなかった。
「道博にこういうことをされるようになるなんてね」
道博が自分を異性として意識していたことによる驚き、弟に生脚を触られた恥ずかしさ、まだまだ子どもだと思っていた道博が成長していたことへの一抹の寂しさと嬉しさ。
節子の中で色々な感情がないまぜになり、節子はポツリとそう呟いた。
その時の節子の表情が、姉としての優しさや愛情、それから色気を帯びたなんとも言えない表情をしていて、道博はさらにグッときてしまう。
「ごめん。見てたら我慢できなくて」
「姉さん、道博のことまだまだ子どもだと思っていたのよ。もう道博も立派な男の人だってこと知らなかった。
姉さん気づかなくてごめんね、無理させちゃってたのね」
「姉さんの脚見てたら、誰でも男になっちゃうよ。こんなに白くてきれいで、色っぽくて、触るとすべすべしてて、……」
いけないことだと今までは自分を抑えていたが、今となっては隠す必要もない。
道博は今までに姉に抱いていた感情を正直に打ち明け、熱っぽい目で姉を見つめる。
「ずっと触っていたくなるよ」
「……道博」
今までに見たことのない弟の表情を見てしまい、節子はその名前を呼ぶだけで精一杯だった。
しばらく二人はそのまま見つめあっていたが、おそらく姉の脚を触る機会もこれで最後だと思うと、道博の気持ちもさらに高まっていく。
節子は他に好きな人がいて、そして何より二人は実の姉弟。今後どうにかなることなんてないだろう。
道博もそれは分かっている。
分かっているからこそ、この時間を大切にしたかった。
「もう少しだけいい?」
道博から尋ねられても、節子は肯定も否定も口にしない。
しとやかにうつむいている節子の成熟した太ももを道博は再びさすり始めた。
先程までは欲望のままにさすっていたが、少しだけ余裕の出てきた道博は、今度はゆっくりと優しく姉の太ももをさする。
手触りも良く、白くて美しいむっちりとした姉の太もも。これで最後だと思うと、自然と道博の手にも熱が入る。
道博の節子への想いは、許されない恋心なのか、それとも性への目覚めなのかは誰にも分からない。
ただ一つ言えることは、どちらにしてもそれは節子の色っぽい脚とむっちりとした太ももにより誘発されたということだ。
「似合うよ、姉さん」
道博は太もものすべらかな感触を刻み付けるように手のひらで味わいながら、時にはテーブルの下で姉のミニスカートの裾を少しだけつまんでみる。
思春期真っ只中の道博には毒になる程の色気だが、節子の美しい脚にそのミニスカートはよく似合っている。デザインも素敵だ。
スカートや脚のことに触れてはいけないと思っていた道博も、ここぞとばかりにその美しさを褒める。
「姉さんは脚が綺麗だから、本当によく似合ってるよ。ミニスカートでも下品にならないからすごい」
「そう、かしら。
それは褒めすぎよ」
「そんなことないよ」
弟に褒められ、恥じらう節子はやはり美しい。
しとやかで落ち着いた女性なのに、恥じらう姿はどこか少女のような愛らしさもある。
人目のあるパーラーなので、精々テーブルの下で脚を触ったり、小声で脚やスカートの話をするぐらいだったか、それだけでも十分道博を興奮させた。
ゆっくりと姉の太ももをさすっていた道博の手も、熱が入ってくるにつれ自然と力強くなり、徐々に激しさを増していく。
ムチムチとした柔らかな感触の太ももの上を道博のしっかりとした大きな手が何度も往復し、ついには感極まって姉の脚をがっしりと掴む。
次第に積極的になってくる弟の手に節子も頬を染めていたが、相変わらず肯定も否定もせず、道博の好きなようにさせている。時折道博の方に少しだけ視線をやるくらいで、節子は恥じらいを秘めたままの表情でうつむいていた。
「本当にきれいな脚だね、姉さん」
とうとう節子のミニスカートの裾の下に手を入れるまでに積極的になってきた道博には、さすがに節子もハッとしたが、それでも節子は道博を止めることはしなかった。ハンドバッグを握りしめ、しとやかにうつむいているだけ。
恋する相手の和彦に体を触られている時とはやはり違うが、自分のことを異性として意識している男性に触られていると思うと妙な気持ちになった。
まだまだ子どもだと思っていた可愛い弟。
その気持ちは今も変わらないし、それ以上の感情はもちろんない。
しかし、可愛い弟がいつのまにか成長していたと思うと感慨深いものがある。そして、それがどんな感情であれ、はっきりとその欲をにじませる手が自分の太ももをいったりきたりするたびに節子の体も熱くなった。
この可愛い弟の気持ちは受け止めることができないけど、はっきりと熱い欲をぶつけられ冷静でいられるほど節子は鈍感ではない。
節子はこの状況に困惑していたが、それほどまでに自分に触れたがっている弟を思うと胸にくるものがあった。
人目があるパーラー。
二人きりで触れ合える場所でもない。
しかし、それがかえって道博の気持ちを燃え上がらせたのかもしれない。
決して触れることはできないと思っていた姉の太ももに自分は今触れている。白くすべすべで、太いわけではないのにむっちりとした肉感のある美しい姉の太ももに。
気持ちが盛り上がるにつれ、それに比例して熱くなり、男性らしい力強さを増していく手つきに節子の方もぐっときてしまう。
早く終わってほしいと思うどころか、なるべく長くこの時間が続いてほしいとさえ思ってしまっていた。
あとがき
姉への思いは、禁断の恋心なのか、ただ単に性への目覚めで一時的な感情なのか。思春期の弟の複雑な心理を描くのが楽しかったです。
まとめ
現代とは違う設定なので難しい部分はあるのですが、ファンタジーや時代物もご依頼者様と設定や表現をご相談の上で書かせていただいております。難しさはあっても、違う世界を表現できるのはとても楽しいですね。もちろん現代物を執筆するのも大好きです。
可愛いものと猫と創作が大好きな物書き。
執筆ジャンルは、恋愛(TL/BL/GL/TSF)、ファンタジー、青春、ヒューマンドラマ、など雑多。年下ヒーローと年下攻めを特に好みます。
簡易プロフィールとリンク集🐱
さらに詳しいプロフィールはこちらから